断裂した前十字靭帯を縫い合わせることは困難であり、たとえ縫い合わせることができても強度が足りず、またすぐに断裂してしまうため、自家組織(移植腱)を使って再建する方法が一般的です。使用する自家組織(移植腱)の採取部位としては主にハムストリング(STG)と骨付き膝蓋腱(BTB)に分かれます。そのほか、大腿四頭筋腱(QT)を採取することもあります。
さまざまなスポーツのアスリートに対し手術が可能
あらゆるスポーツの選手に対し手術を行います。スポーツの種類はアメリカンフットボール、ラグビー、サッカー、バスケットボール、バレーボールなど多様です。
術後のリハビリでは、各競技に合わせた個別プログラムを策定
スポーツは、競技ごとに動きの特性が大きく異なるため、リハビリ段階から競技に合わせたプログラムを組むことが重要です。当院では充実した個別プログラムで復帰をサポートします
靭帯の依存組織を温存し早期復帰を実現
手術では大腿骨側、脛骨側ともに靭帯付着部の遺残組織(レムナント)の温存を心がけています。遺残組織中の血管や神経組織を温存することで早期の血行再開やリモデリングの促進を図り、スムーズな復帰が期待できます。
ハムストリングス(ST-G)を用いた再建術
患者さま自身のハムストリング(半腱様筋腱や薄筋腱)を使って断裂した前十字靭帯を再建します。女性は男性に比べて大腿四頭筋の筋力が弱く、後に紹介する骨付き膝蓋腱を用いた再建術では採取部位の痛みが残存しやすいため、ハムストリングを用いた再建術が第一選択になることが多いです。
メリット
- 移植腱を採取した部位の痛みの残存が少ない
- 骨孔(骨に作製した移植腱が入るトンネル)長に応じて移植腱の長さを調整することができる
デメリット
- 術後に移植腱が伸びると緩みにつながる可能性がある
- ハムストリング(膝を曲げる筋肉)の筋力が落ちやすい
骨付き膝蓋腱(BTB)を用いた再建術
膝の皿(膝蓋骨)の下にある膝蓋腱を使う再建術です。膝蓋腱の上と下にある骨ごと採取し移植腱として用います。ハムストリングを使う(膝を曲げる)動きが多い、柔道やクラシックバレエなどの種目では骨付き膝蓋腱を用いた再建術が推奨されます。
メリット
- 骨同士の癒合によってより強固な移植靭帯の固定が期待できる
- 緩みにくい
デメリット
- 移植腱採取部位の痛みの残存(骨採取部)
- 大腿四頭筋(膝を伸ばす筋肉)の筋力が落ちやすい
大腿四頭筋腱(QT)を用いた再建術
膝の皿(膝蓋骨)の上にある大腿四頭筋腱の一部を使う再建術です。腱の部分だけでなく膝蓋骨に付着する骨の一部も一緒に採取し移植腱として用いることもあります(QTB)。
メリット
- 移植腱を採取した部位の痛みの残存が少ない(腱のみの採取の場合)
- 移植腱の断面積が大きい(BTBとの比較において)
- 骨格的に未熟な小児においても、ハムストリングよりも移植腱として優れている可能性がある
デメリット
- 大腿四頭筋(膝を伸ばす筋肉)の筋力が落ちやすい
- 膝蓋骨骨折発生の可能性がBTBよりも高い(骨も一緒に採取した場合)








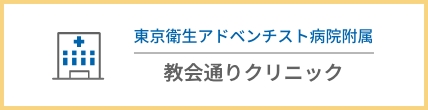

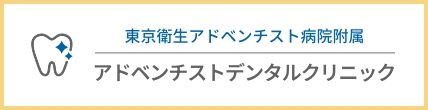
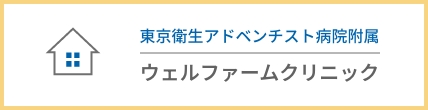
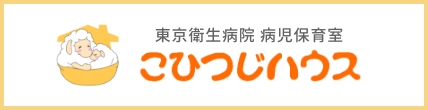


 03-3392-6151
03-3392-6151